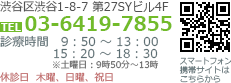花粉症の診断と治療
花粉症とは、スギやヒノキなどの植物抗原(アレルゲン)が粘膜に付着してアレルギー反応を起こすことによって、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの鼻炎症状や眼の痒みを引きおこす季節性のアレルギー性炎症です。
アレルゲンに対して産生されたIgE抗体が細胞の表面に結合し、ここにアレルゲンが再度接触すると、細胞が刺激されてヒスタミンやロイコトリエンを放出する結果、鼻水・涙や鼻づまりを起こします。衣類や、眼・鼻を洗うことに気をつけて、アレルゲンとの接触をできるだけ減らすことが大切です。
治療は、抗アレルギー薬と呼ばれる一連の薬剤を服用したり、点鼻薬・点眼薬などの局所投与薬を組み合わせて行います。さらに、食生活や睡眠に注意することで、身体の免疫力をバランスの取れた適切な状態に保つことも大切です。
どんな病気?
空気から吸入される様々な物質の中の一部のタンパク質が抗原(アレルゲン)となり、鼻の粘膜でアレルギー反応が引き起こされ、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状が起きる病気をアレルギー性鼻炎といいます。例えば、ハウスダストによるアレルギー性鼻炎は、症状が1年中起きるので通年性鼻炎と呼ばれるのに対して、花粉による鼻炎は季節性に症状が出るので、季節性アレルギー性鼻炎に分類されます。さらに、アレルゲンが眼の粘膜に付着して同様の反応を引き起こせば、眼の充血や痒みがおきます(アレルギー性結膜炎)。
花粉症とは、スギやヒノキなどの植物の花粉に含まれるアレルゲンがこれらの粘膜に付着することがきっかけでアレルギー反応が起きる結果、鼻や眼に症状を引き起こす病気です。
どうして起きるの?
私たちの身体がスギやヒノキに敏感になるというのは、具体的には、スギやヒノキの花粉のタンパク質(アレルゲン)に対して、IgE抗体と呼ばれるタンパク質を身体が産生するようになることを意味しています。
通常私たちの身体で作られるIgG抗体、IgA抗体は、感染した細菌を排除する免疫機能の一端を担っていますが、IgE抗体はアレルギー反応に関連した抗体です。このIgE抗体は、マスト細胞(肥満細胞)と呼ばれる細胞の膜の上にある受容体に結合して、アンテナのようにアレルゲンを待ち構えています。この状態を、スギやヒノキに“感作された”といいます。
感作された状態の人が花粉抗原に再び暴露されると、鼻や眼の粘膜に分布している肥満細胞の上に出ているアンテナに花粉アレルゲンが結合するために細胞が活性化されて、細胞の中からヒスタミンやロイコトリエンなどの様々な物質が放出されます。ヒスタミンはくしゃみ反射を起こし、粘液の分泌を亢進させて鼻水や涙を作りだします。ロイコトリエンが作用すると血液の流れが滞り、鼻づまりを起こします。
患者さんがどのアレルゲンに感作されているか、すなわちどのアレルゲンに対するIgE抗体を産生して体内に持っているかについては、血液検査で調べることが可能です。
どうすればいいの?
花粉症対策でまず大事なことは、可能な限り原因アレルゲンに暴露されないことです。花粉の飛散の激しい日には、可能であれば外出を避けるのが望ましいのですが、現実の生活をしている以上、そうもいきません。そこで、外出から帰って来た時には、家の中に入る前に衣類をよく叩き、付着している花粉を落とすようにしましょう。ウール系の衣類には花粉が付きやすいので、できれば避けてください。さらに、家に入ったら、まず、手、顔や眼を洗い、少しでも粘膜と花粉とが接触しないように努めます。鼻を洗浄するための道具と洗浄用の薬品も市販されているので、これを用いて鼻腔を洗浄するのも良いでしょう。
起きてしまった症状に対しては、ヒスタミンやロイコトリエンの作用を抑える薬などを用います。よく用いられるのが、第二世代の抗アレルギー薬とよばれる一群の薬剤です。抗ヒスタミン作用によりヒスタミンの作用をブロックして、くしゃみや鼻水を抑制する効果があります。ただし、この薬剤で問題となるのが、副作用としての眠気・だるさです。薬の種類によって、眠気が出やすいものから出にくいものまで様々に分類されています。ただし、眠気が強い薬であっても、その薬で眠気が出る頻度はおよそ7~10%くらいで、9割の患者さんでは眠気を自覚しません。一方、眠気の少ないと言われている薬でも、ある一定の割合で患者さんは眠気を自覚します。
そこで、経口の抗アレルギー薬は、個々の患者さんそれぞれで、効果と眠気・だるさを見ながら最適なものを決めてゆくことが必要になります。経口薬を飲むほどではない患者さん、あるいは経口薬だけでは効果が不十分な患者さんには、点眼薬、点鼻薬などのいわゆる局所投与薬を投与します。抗アレルギー薬以外に、局所投与のステロイド薬もあります。耳鼻科の専門医の中には、気管支喘息の治療で吸入ステロイドが基本薬であるのと同様に、花粉症でも点鼻ステロイド薬をもっと積極的に使うべきであると言う方もいます。症状が極めて激しくて、生活や仕事上どうしても症状を抑える必要がある時には、短期間に限って経口ステロイド薬を投与する場合もありますが、投与量や投与期間については専門医がしっかりフォローすることが必要です。
この他に、原因となるアレルゲンを身体に少しずつ投与することで過剰な反応をおこさないようにする“減感作療法”も一部の施設では行われています。最近では、スギ花粉のエキスをパンなどの切れに浸して舌の付け根を潤すことを毎日繰り返す“舌下免疫療法”が注目され、一部の専門医により実施されています。今後はスギアレルゲンだけでなく、ハウスダストを用いた舌下免疫療法が開発されつつあります。
花粉症は予防できないの?
現時点では、明らかに科学的効果の立証された予防法はありません。しかし、アレルギー反応を制御する可能性が期待されているものもあります。
その一つが腸内細菌です。善玉菌である乳酸菌をマウスに食べさせると、下気道のアレルギー疾患である気管支喘息の発症を抑制したという実験報告も出されています。実は、免疫を司る重要な細胞の一つであるリンパ球は、全体の75%が腸管に集まっており、腸管は人体で最大の免疫器官であると見なすことができるのです。さらに、腸管の中に寄生する腸内細菌が、私たちの免疫機能に影響を与えることも判ってきています。
そこで、腸内細菌の環境を適正な状態に保つことで免疫のバランスを整え、それによって過剰なアレルギー反応を抑制することが理論的には可能と考えられています。ただし、例えばビフィズス菌を含む食品を食べれば確実に腸内細菌環境が良くなるかは、食べる量や他の食材の影響もあるので、簡単に結論を出すことはできません。
この他、免疫機能を適正に維持するという点では、適切な睡眠や規則正しい生活リズムなども影響します。花粉症で悩んでいる方は、自分の生活習慣を見直してみるのも良いと思います。トータルライフケアの考えにもとづいて、日々の生活を整えることも、様々な薬を使うことと同じくらい大切です。