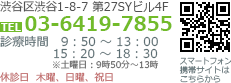花粉症と気管支喘息との関係
花粉症と気管支喘息の関係:”One airway, one disease”
最近では、気管支喘息と花粉症・アレルギー性鼻炎とは、気道に起きるアレルギー性疾患という点から類似した病気と考えられるようになりました。2010年に行われた約2万人を対象とした全国調査でも、喘息の患者さんの約3分の2に同時にアレルギー性鼻炎の症状があり、逆にアレルギー性鼻炎の患者さんの3分の1には喘息症状がありました。
鼻腔(上気道)と気管支(下気道)とは解剖学的に連続しています。例えば、スギ花粉そのものは粒子の大きさの点から鼻の粘膜に留まり、気管支にまでは到達しません。しかし、スギ花粉により鼻でアレルギー性の炎症が起きると、その場で様々な炎症性細胞が活性化されます。すると一部の細胞は血流に乗って気管支に達し、そこで炎症を起こします。丁度、強い風に煽られて火の粉が飛び散り、離れたところで火事を起こすのに似ています。
あるいは、細胞自身でなくても、炎症細胞の増加や活性化を引き起こす分子が気管支に到達して炎症を引き起こすことも考えられます。実際に患者さんでこのことを検討した報告もあります。花粉症のあるボランティアの鼻の粘膜に花粉抗原を垂らし、その後数時間してから気管支鏡で気管支の中を調べてみると、好酸球という、アレルギーに関係した白血球が増えていることがわかりました。逆に、アレルギー性鼻炎の症状の全く無い気管支喘息単独の患者さんの気管支に、気管支鏡で抗原を滴下してから数時間後に鼻の粘膜を調べると、同じように好酸球が増えていることもわかりました。
すなわち、アレルギー性鼻炎でも気管支喘息でも、潜在的には鼻にも気管支にも炎症細胞の流入と活性化が同時に起きている可能性が示唆されました。このことを表すのが”one airway, one disease”という言葉であり、鼻と気管支が解剖学的に繋がっている以上、アレルギー性鼻炎と気管支喘息とは、共通した気道の病気であるということを意味しています。そこで最近では、「気管支喘息」という用語から「気管支」を外して「喘息」と呼ぶことも提唱されています。
”one airway, one disease”の考え方によれば、鼻と気管支のアレルギーは同時に治療した方が治療効果が高いということになります。
実際に、アレルギー性鼻炎を合併している気管支喘息の患者さんに鼻炎の治療を同時に行うと、鼻炎を同時に治療しなかった群に比べて、統計学的に明らかに喘息症状のコントロールが良くなり、発作を起こして薬を余分に使うことが少なくなり、救急外来の受診回数が減り、結果として喘息に用いた治療費も少なくて済んだということが多くの国から報告されています。さらに踏み込んだ言い方をすれば、喘息患者は潜在的に鼻炎を合併しており、鼻炎患者は潜在的に喘息の予備軍と考えることができます。
花粉症のシーズンが経過するとともに、鼻や眼の症状だけでなく咳や気管支の違和感を感じ始めた患者さんは、気管支にもアレルギー性炎症が起きてきたと考えて下さい。この場合、花粉症の治療に通常用いる経口の抗アレルギー薬や点鼻薬・点眼薬だけでは気管支の症状はなかなか治まりません。下気道の炎症に対して喘息の治療に使う吸入ステロイド薬を併用することが必要であり、有効です。